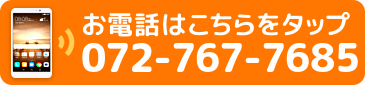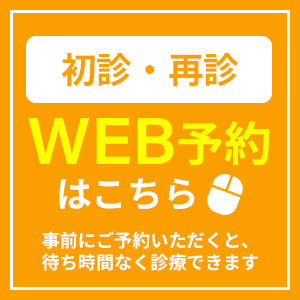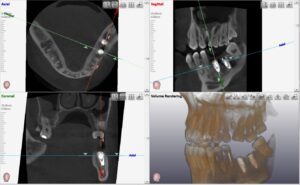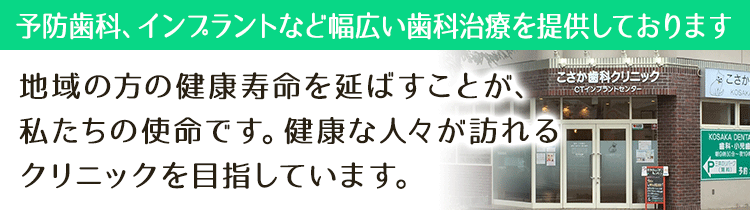こんにちは、こさか歯科クリニックです。
今回は、ホワイトニングの薬剤がどのようにして歯に作用し、白くしていくのか説明していきます。
ホワイトニング施術写真

ホワイトニング術前写真

オフィスホワイトニングでは、薬剤を歯面に塗布した後、このように専用のライトを照射します。

オフィスホワイトニング術後写真。
過酸化水素・過酸化尿素によるホワイトニングの仕組み
・フリーラジカルによる作用
ホワイトニング剤に含まれる過酸化水素(HP)・過酸化尿素(CP)を歯面に塗布すると、口腔内で分解され、フリーラジカルを発生します。
このとき、熱を加えるとより反応が促進されるので、オフィスホワイトニングでは専用のライト照射を行なっています。
過酸化尿素は過酸化水素と尿素が弱く結合した物質であり、唾液中の水分との接触と温度により、尿素と過酸化水素水に分解します。
これらの色素分子が、歯の着色の原因となっている色素分子と結合して、無色透明にさせることで歯が白くなります。このうち、過酸化水素の方が過酸化尿素より分解が早く、効果は早くあらわれるがなくなるのも早いという特徴があります。このため、オフィスホワイトニングでよく使用されます。逆に、過酸化尿素はホームホワイトニングに配合されていることが多いです。
・マスキング効果
ホワイトニングシステムによりますが、使用薬剤の成分により一時的に歯のカルシウム成分が溶け出して、エナメル質の表面が凸凹になる現象が起きます。その結果、光の乱反射がしょうじ、内部の象牙質の色が見えにくくなる「すりガラス状」になり、歯が白く見えるのがマスキング効果と呼ばれます。しかし、数時間のうちにカルシウムが元に戻るため、マスキング効果は一時的なものです。
・歯の乾燥+ペリクルが剥がれることによるもの
ホワイトニング直後は歯のペリクル(タンパク質の保護膜)が一時的に剥がれ、歯が乾燥しているため表面が白っぽく見える現象があります。ペリクルが再生する24時間程度で元に戻ります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ホワイトニング剤の成分
歯科用ホワイトニング剤は各社から出されていますが、基本的に以下のような成分で構成されています。
・有効成分
過酸化水素
過酸化尿素
・基剤:マトリックスキャリア
過酸化水素・過酸化尿素を含ませる、ベースとなる材料のことです。ホワイトニング剤の性状は、歯面に塗布した時を考えると、適度な流動性を持ち、尚且つ塗布しやすいことが重要です。歯肉に流れてしまうようなフローが良い状態は望ましくありません。シリカ、グリセリン、ポリアクリル酸などが挙げられます。
・知覚過敏抑制剤
硝酸カルシウム、酸化アルミニウムなどです。ホワイトニング施術による知覚過敏を抑制する効果があります。
・その他の成分
炭酸水素ナトリウム、クエン酸、香料、中性フッ化ナトリウムなど。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ホワイトニング効果を上げるために必要なこと
以下のような点が大切です。
・歯のクリーニング
薬剤の有効成分を十分作用させるため、事前のクリーニングを徹底的に行います。
・過酸化水素、過酸化尿素
これらの有効成分の濃度を高めることは重要です。一般的に高濃度は効果が高いですが、そのかわりしみやすい副作用があります。
・作用時間
時間が長いほど反応は進みます。ただし、分解が終わるとそれ以上は反応しません。メーカー推奨の使用時間が効果的であり、延長すれば良いというわけではないようです。
・アルカリ性の環境
ホワイトニング剤が反応するpHは、アルカリ性の方が反応がよく、効果が期待できます。このため、水酸化カルシウムなどのアルカリ性薬剤を歯面に塗っておく方法もあります。
・加熱
熱により反応スピードが上がります。10℃上がると2倍のスピードになると考えられています。オフィスホワイトニングで専用ライトを照射し、お口周りをタオルでカバーしますが、加熱効果を期待しています。照射のライトがまぶしいため、目隠しのゴーグルやタオルもします。ライトで熱を加え過ぎると痛みも出やすくなるため、注意が必要です。オフィスホワイトニング直前に、薬剤のジェルは熱湯につけて温めて使用します。

オフィスホワイトニングで、薬剤を歯面に塗布する直前までこのように沸騰したお湯に薬剤をつけています。
・密閉環境
ホワイトニングは、フリーラジカルがいかに歯質に多く入り込むかで効果が決まります。密閉環境の方が、分解したフリーラジカルが大気中に飛ばずに、歯質内に入り込む確率が高まります。そのため、ホームホワイトニングの場合はマウスピースで空気に触れにくくできますので密閉効果が期待できます。オフィスホワイトニングでは、密閉することができません。

オフィスホワイトニングはこのように歯面に薬剤を塗布しますので、解放されています。

ホームホワイトニングはマウスピース内部にジェルを入れて、歯に密接するように作用させますので、密閉された効果が大きいです。
・消費期限
ホワイトニングジェルは、時間が経つと効果が弱まります。成分が分解するためです。標準的な保存期間は約1年半ですが、メーカーにより異なります。

私たちが使用しているポリリン酸ホワイトニングのジェルは、このような個別包装になっており、保存期間よりも前に使い切れます。
また、保管温度にも影響を受けます。冷暗所が望ましいので、冷蔵庫に保管をしています。ホワイトニングに限らず、歯科材料には適正な室内温度があるため、それぞれの材料の特性を活かすためには、添付文書に記載されている事項に注意して取り扱うのが間違いないです。歯科材料でよくあるのが、粉と液、A液とB液を混和し、使用することです。目分量で使用するのはダメですね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オフィスホワイトニングとホームホワイトニングの違い
・オフィスホワイトニング
歯科有資格者の管理下で行われる安全なホワイトニングです。30〜35%の過酸化水素配合ジェルとライトを使用します。
✳︎メリット
即効性が高い
1回の来院である程度白くできる
自分で管理しなくて良い
✳︎デメリット
効果の持続が3〜6ヶ月と、ホームホワイトニングよりも短い
奥歯は白くできない
白さの限界がB1シェード
・ホームホワイトニング
10〜15%の過酸化尿素、または過酸化水素のジェルをマウスピースに入れ、自宅で行なってもらう方法です。
✳︎メリット
効果が長持ちする。半年から1年程度。
色むらが取れ、つやや透明感が出る。
通院回数が少ない
白さの限界値がオフィスのみより高い。
✳︎デメリット
自分で管理しなければならない。
効果が出るまで時間がかかる。
・デュアルホワイトニング
オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを併用する方法です。クリーニングを同時に行うことで、さらに効果が高まります。オフィスホワイトニング、ホームホワイトニング両方のデメリットを補える最良の方法と考えられます。目標達成率も高いです。
効果が持続しやすいですし、クリニックで専門的な管理のもとで行えるメリットが大きいです。
ホワイトニングは気軽に始められるものですが、歯の状態によっては事前の清掃や病気があった場合の治療が必要かもしれませんので、
まずはお問合せしていただき、口腔内の診察からさせていただきます。